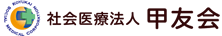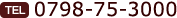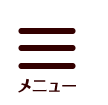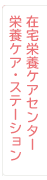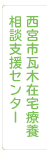指針
安全管理指針
- 安全管理に関する基本的な考え方
(1) 医療事故を未然に防ぐという強い信念のもと、当院での医療事故“ゼロ”を最終目標にして、より質の高い医療を提供する医療環境を整える。 (2) 「人はエラーを犯すもの」という認識に立ち、発生した誤りが事故に結びつかない医療環境、標準となる手順、組織体制を整える。 (3) 事例に学ぶという姿勢を重視し、発生した誤りを積極的かつ主体的に報告する医療従事者の認識と職場環境を整える。
また、報告された内容を分析し、誤りが医療事故につながらない体制を整えて再発の防止に努める。(4) 医療の内容や枠組みが日々変化し発展するなかで、常に新たな医療事故発生の可能性があることを認識し、これを未然に防ぐよう努める。 (5) 医療の質の向上を目指した組織的な取り組みを堅持し、患者さまが安全な医療を受けられる医療環境を整える。 - 安全管理に関する組織体制
(1)安全管理委員会
(2)医療安全管理者
(3)医薬品安全管理者
(4)医療機器安全管理者
(5)医療ガス安全管理委員会
(6)危機管理委員会 - 安全管理および推進のための各種マニュアルなどの整備
(1) 安全管理マニュアルなどの作成は、多くの職員がその作成・検討に関わることを通じて、職場全体に日常診療における危険予知、患者さまの安全に対する意識、事故を未然に防ぐ意識などを高め、広めるという効果が期待される。
全ての職員はこの趣旨をよく理解し、マニュアルの作成に積極的に参加しなくてはならない。(2) 安全管理マニュアルなどの作成、その他、医療の安全、患者さまの安全確保に関する議論においては、全ての職員はその職種、資格、職位の上下に関わらず対等な立場で議論し、相互の意見を尊重する。 (3) 安全管理のためには、業務プロセスを標準化(マニュアル化)し、それを職員が道具として使いこなすことが重要である。
業務プロセスを一つひとつ見直し、標準手順(マニュアル)を作成する際には安全手順を必ず挿入することとする。 - 安全管理および推進のための職員研修
医療に係る安全管理の基本的な考え方および具体的方策を全職員に周知徹底することを通じて、職員個々の安全管理に対する意識を高めるとともに、当院全体の医療安全を向上させることを目的とする。 - 報告などに基づく医療安全確保のための改善方策
報告は医療安全を確保するためのシステムの改善や教育・研修の資料とすることのみに使用する。
報告を行った職員に対しては、これを理由として不利益な取扱いを行ってはならない。 - 医療事故発生時の対応
(1) 医療側に過失があるか否かを問わず、患者さまに有害事象が生じた場合には、院内の総力を結集して患者さまの救命と被害の拡大防止に全力を尽くす。 (2) 医療事故が発生した場合は、過失の有無に関わらず、患者さまおよびご家族などに対して誠実で透明性のある対応を行うことを第一に心がける。 (3) 特に医療過誤の可能性のある場合は、事実の隠蔽・秘匿につながる行為は絶対行わないように注意する。 - 患者さまからの相談への対応
安全で質の高い医療の提供と医療サービスの向上および患者さま・ご家族などと病院のより良い信頼関係がつくられることを目的に、院内に患者相談窓口を常設する。
また、この指針は院内に掲示し、患者さまおよびご家族から閲覧の求めがあった場合は、これに応じます。
安全管理委員会
身体拘束などの適正化のための指針
- 基本理念
当院は、患者さまに対し適切な診療・看護・介護・リハビリテーションを提供する必要があり、不要な身体拘束により身体改善へ妨げになってはならない。
身体拘束は、患者さまの生活の自由を制限するものであり、患者さまの尊厳ある生活を阻むものである。
よって、患者さまの尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく職員一人ひとりが身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識を持ち、身体拘束をしない支援の実施に努める。 - 身体拘束などの適正化に関する基本的な考え方
(1) 身体拘束およびその他の行動を制限する行為の原則禁止 (2) 身体拘束などを行う基準
やむを得ず身体拘束などを行う場合は、以下の3要件を全て満たす必要があり、その場合であっても身体拘束などを行う判断は、組織的かつ慎重に行う。
切 迫 性: 患者さま本人または他の患者さまなどの生命、身体、権利が危険にさらされる可能性が著しく高いこと 非代替性: 身体拘束などを行う以外に代替する方法がないこと 一 時 性: 身体拘束などが一時的であること (3) 鎮静を目的とした薬物の適正使用 (4) 肢体不自由、特に体幹機能障害がある患者さまに対しての体幹保持などに関してベルト類などを装着する行為は、「やむを得ない身体拘束など」ではない。
その行為を行わないことが、かえって患者さまが危険な状態に陥るため虐待に該当すると留意する。 - 身体拘束などの適正化に向けた組織体制
身体拘束最小化チームを安全管理委員会内に設置し、身体拘束最小化に向けて、支援現場における諸課題の統括を行う。 - 身体拘束などの適正化推進への職員研修
身体拘束など廃止と人権を尊重したケアの励行および安全管理の基本的な考えを入院患者さまに関わる職員を対象とした研修会・教育を年1回以上実施する。 - 患者さまなどに対する当該指針の閲覧に関する基本方針
指針は院内に掲示し、患者さまおよびご家族から閲覧の求めがあった場合はこれに応じます。 - その他の当院における身体拘束など適正化への推進に必要な基本方針
身体拘束など適正化推進のため「身体拘束などの適正化のための指針」を作成し、病院職員への周知徹底を図ると共に、マニュアルの見直し・改訂を行います。
安全管理委員会(身体拘束最小化チーム)
院内感染防止対策指針
- 院内感染防止対策に関する基本的考え方
感染防止対策は、安心・安全な医療提供の基盤となるものです。
当院は、感染防止対策を病院全体として取り組み、病院に関わる全ての人々を対象として、院内感染発生の予防と発生時の速やかな対応を行うことに努めます。 - 院内感染防止対策のための委員会などの組織に関する基本的事項
当院における感染防止対策に関する意思決定機関として、院内感染防止対策委員会を設置し、毎月1回会議を開催し感染防止対策に関する事項を検討します。
また、感染制御チーム(ICT)を委員会内に設置し、感染防止対策の実務を行います。 - 院内感染防止対策のための従事者に対する研修に関する基本方針
職員の感染防止対策に対する意識・知識・技術向上を図るため、全職員を対象とした研修会・講習会を年2回以上行っています。 - 感染症の発生状況の報告に関する基本事項
法令に定められた感染症届出の他、院内における耐性菌などに関する感染情報レポートを作成し、感染制御チーム(ICT)での検討および現場へのフィードバックを実施しています。 - 院内感染発生時の対応に関する基本事項
感染症が発生または疑われる場合は、感染制御チーム(ICT)が感染対策に速やかに対応します。
また必要に応じ、通常から協力関係にある地域の他医療機関や保健所と速やかに連携し対応します。 - 患者さまなどに対する当該指針の閲覧に関する基本方針
本取組事項は院内に掲示し、患者さまおよびご家族から閲覧の求めがあった場合はこれに応じます。 - その他の当院における院内感染防止対策の推進に必要な基本事項
院内感染防止対策の推進のため「院内感染防止対策マニュアル」を作成し、病院職員への周知徹底を図ると伴に、マニュアルの見直し・改訂を行います。
院内感染防止対策委員会